チームメンバーの能力レベルで見極める
チームを動かす「3つの目標」:あなたの会社はどれですか?
チームで成果を出すには「目標」が欠かせません。
ですが、一口に「目標」と言っても、実は3つの種類があることをご存知ですか?
これを理解しないまま目標を立てると、「メンバーが思うように動いてくれない」「指示待ちばかりで、新しいアイデアが出てこない」といった悩みにつながりがちです。
御社の目標は、次のどれに近いか、ちょっと想像しながら読んでみてください。
事例:商店街の小さな定食屋さんの挑戦
例えば、従業員5名の小さな定食屋さんが「もっとお店を繁盛させたい」と考えたとします。
このとき、目標の立て方には3つのレベルがあります。
A:行動レベル(やるコト目標) 「新メニュー『日替わり満腹ランチ』を開発し、毎日50食つくる」
B:成果レベル(結果目標) 「ランチタイムの売上を、今月中に30%アップさせる」
C:意義レベル(あり方目標) 「『この街の台所』として、地域の人々のお腹と心を満たす存在になる」
このA・B・C、どれが良くてどれが悪い、というわけではありません。
それぞれに得意なこと(メリット)と苦手なこと(デメリット)があるんです。
3つの目標、それぞれの「得意」と「苦手」
A:行動レベル(やるコト目標):「何をやるか」がハッキリ
これは「今日、何をすればいいか」がとても分かりやすい目標です。
・得意なこと(メリット) 「『日替わり満腹ランチを50食つくる』と言われれば、新入りのアルバイトさんでも、仕込みや調理の手順さえ覚えればすぐに動けます。
「何をやればいいんだろう?」と迷う時間がありません。
・苦手なこと(デメリット) 「50食つくる」ことがゴールになってしまいがちです。
例えば、大雨でお客さんが少ない日でも「目標だから」と50食つくってしまい、たくさん売れ残るかもしれません。
言われたこと以上の工夫や「ちょっと待てよ?」という改善が生まれにくいのが弱点です。
C:意義レベル(あり方目標):「なぜやるか」で心に火がつく
これは「私たちが目指す、最終的な姿」を示す、大きな目標です。
・得意なこと(メリット) 「『この街の台所になる』という大きな目標があると、メンバーのやる気に火がつきやすくなります。「よし、そのために何ができる?」と、みんなが考え始めます。
「ランチだけじゃなく、お年寄り向けの宅配弁当も喜ばれるかも?」 「子供連れでも来やすいように、小上がり席をきれいにしよう」 …こんな風に、指示されていなくても、思いがけない素晴らしいアイデア(ブレイクスルー)が飛び出す可能性があります。
・苦手なこと(デメリット) これだけだと、「で、具体的に何から手をつければ?」と途方に暮れてしまう危険があります。
「『街の台所』かぁ…壮大だな…」と考えるだけで終わってしまい、結局、昨日と同じ仕事をするだけ、ということにもなりかねません。
B:成果レベル(結果目標):バランス型の「結果」目標
これは、A(やるコト)と C(あり方)の、ちょうど中間に位置する目標です。
・特徴 「『売上30%アップ』という結果を出す」のが目標です。
Aの「ランチを50食つくる」だけでは、達成できるか分かりません。
売れ残ったらダメだからです。 Cの「街の台所になる」ほど、ぼんやりもしていません。
「30%アップ」という結果を出すために、「ランチの数を調整しようか?」「新しい看板を作ろうか?」「夜のつまみメニューを増やそうか?」と、具体的な行動(A)を考える「きっかけ」になります。
あなたのチームに合うのは、どの目標?
では、この3つの目標をどう使い分ければいいのでしょうか?
答えは、「あなたのチームの今の状態に合わせる」です。
・チームがまだ成長中の場合(新人・若手が多い)
メンバーがまだ仕事に慣れていなかったり、自分で考えて動くのが苦手だったりする場合は、Aの「行動レベル(やるコト目標)」をしっかり示すことが大事です。
「『街の台所』を目指そう!(C)」とだけ伝えても、動けません。 まずは「このレシピ通りに、この手順で、ランチを50食つくってみよう(A)」と、具体的な行動を指示し、場合によってはマニュアルを整備してあげる必要があります。
まずは「できる」ことを増やしてあげるのが先決です。
・チームがベテラン揃いの場合(自ら考え動ける)
メンバーが経験豊富で、自分で考えて動ける人たちなら、むしろ細かいA(行動レベル)は邪魔になることさえあります。
そういうチームには、Cの「意義レベル(あり方目標)」やBの「成果レベル(結果目標)」をドンと任せてみましょう。
「『街の台所』になるために(C)、今月は『売上30%アップ』を目指したい(B)。
どうすれば達成できるか、みんなの知恵を貸してほしい」 こう問いかければ、店長が思いつきもしなかったような、現場ならではの素晴らしいアイデアが次々と出てくるはずです。
任せることで、チームの力は最大化されます。
まとめ:目標設定は「チームに合わせる服」
チームの力を引き出す目標設定とは、A・B・Cのどれか1つを選ぶことではありません。
それは、チームの今の「体格」(=メンバーの力や経験)に合わせて、ピッタリの服を選ぶ作業に似ています。
・まだ小さい子(成長中のチーム)には、動きやすいように具体的な服(行動目標)を。
・大人(ベテランチーム)には、その人のセンスが活きるような服(意義目標)を。
時には、3つすべてを「C(あり方)のために、B(結果)を目指し、そのためにまずA(行動)から始めよう!」と、つなげて伝えることも必要です。
ぜひ一度、あなたのチームの「今」を見つめ直し、どのレベルの目標を伝えるのが一番力が発揮できるか、考えてみてください。
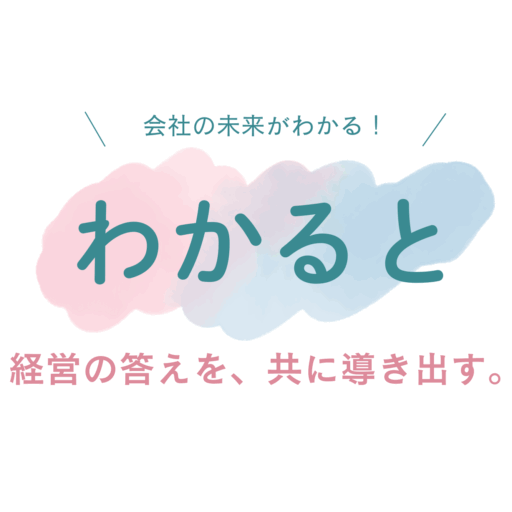
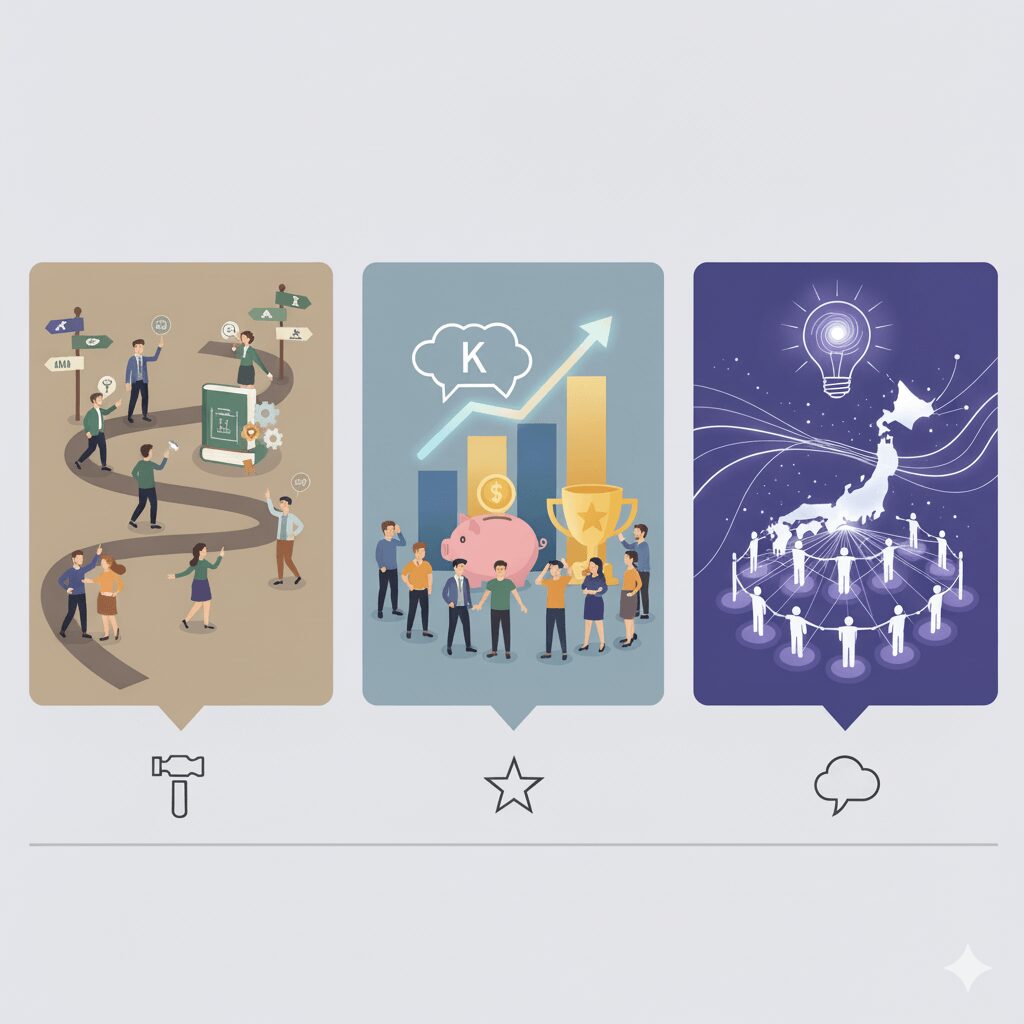



コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://wakaruto.jp/%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e7%9b%ae%e6%a8%99%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%ae%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/trackback/