チーム目標設定の重要性
「今日のラッキーカラーは赤!」と朝の占いで言われると、不思議と街中で赤い車や看板が目に飛び込んできませんか?
これは、心理学で「カラーバス効果」と呼ばれる現象です。
何かを意識すると、脳がアンテナを立てたように、それに関連する情報を自然と集め始めるのです。
仕事のチームもこれと全く同じです。チームが「何を大切にするか」「どこを目指すのか」という目的意識(=目標)を持つことで、メンバー一人ひとりのアンテナの向きが揃い、日々の仕事の中で何に注目し、どう考え、どう行動するかが劇的に変わります。
まさに、チームにとって目標は、航海の成功を左右する「羅針盤」のようなものなのです。
「どう漕ぐか?」の前に、「どの島へ向かうか?」を決めよう
多くのチームが、「どうすれば目標を達成できるか?(How)」、つまり「どうすれば船を速く漕げるか?」という議論に多くの時間を費やしてしまいます。
もちろん、効率的な漕ぎ方も重要です。
しかし、それよりもっと根本的に大切なことがあります。
それは、「そもそも、どの島(目標)へ向かうのか?(What)」を全員で明確にすることです。
もし、目指す島が間違っていたら、どんなに一生懸命、必死に船を漕いでも、永遠にたどり着くことはできません。
それどころか、望まない場所へ向かってしまうかもしれません。
だからこそ、「どんな目標を立てるか」に、私たちはもっと情熱と時間を注ぐべきなのです。
良いチームとは、「目標達成能力が高いチーム」である前に、「自分たちにとって最高の目標を設定できるチーム」なのです。
「やらされ目標」から「私たちの目標」へ
私たちは、学生時代からテストの点数や部活動の順位など、「与えられた目標」をクリアすることに慣れています。
しかし、ビジネスの世界、特に少数精鋭で戦う中小企業においては、この「受け身」の姿勢がチームの成長を妨げる大きな壁になることがあります。
社長やリーダーがトップダウンで決めた目標は、一見効率的に思えるかもしれません。
しかし、そこには「やらされ感」が生まれやすく、メンバーの本当の力やアイデアを引き出すことは難しいでしょう。
チームづくりで本当に大切なのは、「自分たちで最適な目標を設定する」という意識です。
なぜ「自分たちで」決めるとうまくいくのか?
納得感が「自分ごと」を生む
自分たちで話し合い、悩み、決めた目標だからこそ、一人ひとりが「これは自分たちの目標だ」と強く感じることができます。
この「自分ごと」化こそが、主体性と責任感の源泉になります。
現場の知恵が「生きた目標」をつくる
お客様に一番近い場所で働くメンバーの意見やアイデアを取り入れることで、机上の空論ではない、現実的で、かつ挑戦しがいのある「生きた目標」を立てることができます。
同じ船に乗る「一体感」が生まれる
目標設定のプロセスを全員で共有することで、「私たちは同じ目的地を目指す仲間なんだ」という強い一体感が生まれます。
困難な状況に直面しても、この一体感がチームを支える大きな力となるのです。
まずは小さな一歩で構いません。
「次の3ヶ月、私たちチームは何を一番大切にしようか?」そんな問いをチーム全員で話し合う場を設けてみてはいかがでしょうか。
その対話こそが、最強のチームをつくるための、最も確実な航海の始まりとなるはずです。
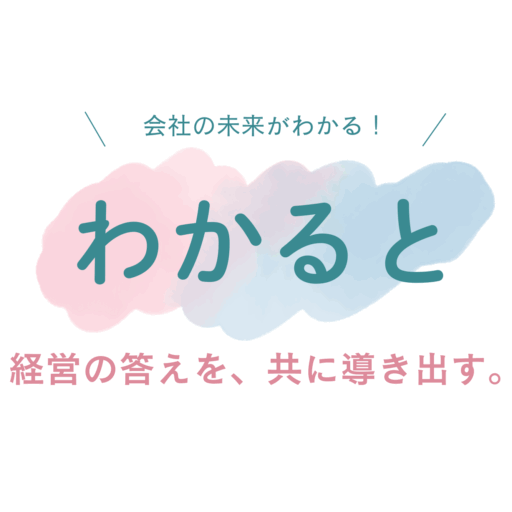




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://wakaruto.jp/%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%ae%e6%a8%99%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e7%be%85%e9%87%9d/trackback/